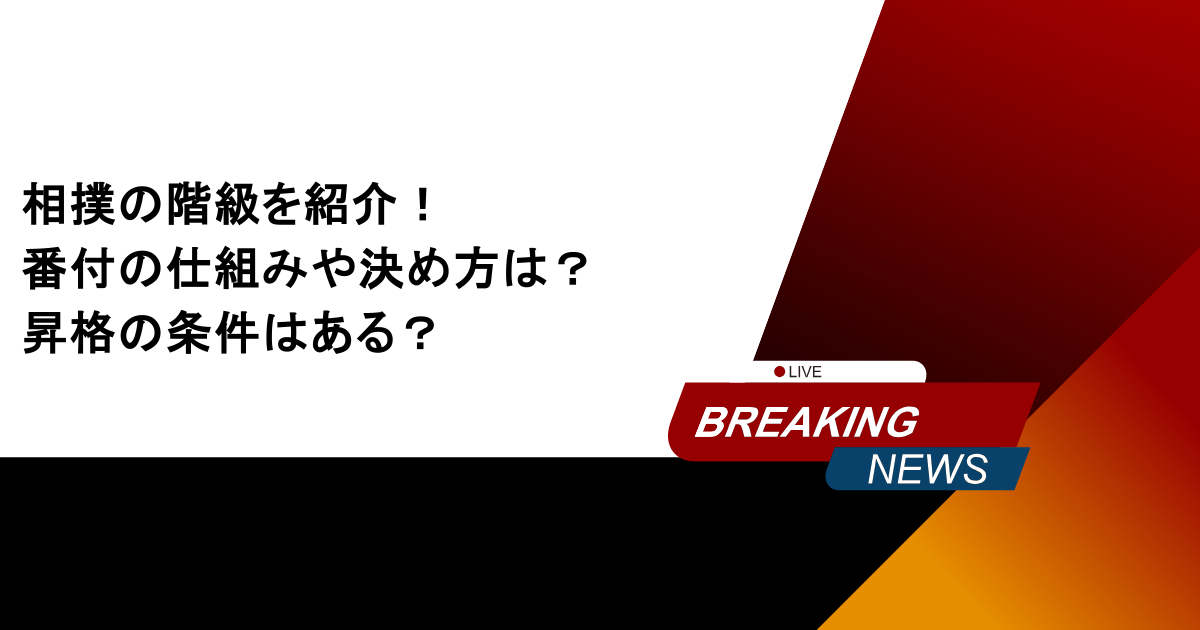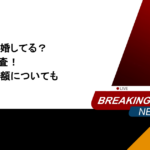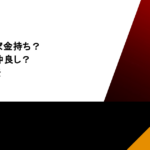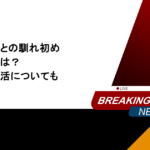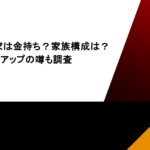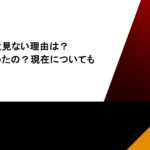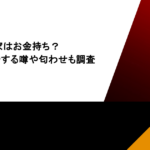相撲といえば日本の国技として世界中に知られていますが、実はその世界には複雑かつ厳格な「階級制度(番付)」が存在します。「横綱」や「大関」などの名称を聞いたことがある人も多いと思いますが、それがどうやって決まるのか、どんな仕組みなのかは意外と知られていませんよね?本記事では、相撲の階級(番付)の仕組み、番付の決め方や昇格・降格の条件などを、初心者でもわかりやすく詳しく解説していきます。
Contents
相撲の階級(番付)とは?全体の構造を解説
相撲の世界では、力士の実力に応じて階級(=番付)が細かく分かれており、全力士がその中でランキングされます。この階級は相撲協会によって公式に発表され、毎場所ごとに更新されます。相撲の階級は、実力に応じて細かく分類されており、それぞれに定員数が設けられています。以下の表で、その構成を見てみましょう。
| 階級 | おおよその定員数 |
| 幕内(まくうち) | 42名 |
| 十両(じゅうりょう) | 28名 |
| 幕下(まくした) | 約120名 |
| 三段目(さんだんめ) | 約200名 |
| 序二段(じょにだん) | 制限なし |
| 序ノ口(じょのくち) | 制限なし |
上位の階級になるほど人数が絞られており、狭き門となっているのが特徴で、相撲のオッズも高い人気を誇っています。
十両がボーダーライン
相撲界で力士の扱いが大きく変わるのは、何といっても「十両以上かどうか」という点です。十両以上の力士は「関取(せきとり)」と呼ばれ、以下のような待遇が一変します。
- 給料(本俸)が支給される
- 個室が与えられ、付き人がつく
- 着用できる着物や帯の格式も変わる
- 取り組みもテレビ中継される
各階級の構成と待遇
相撲の階級の構成と待遇を見ていきましょう。
横綱(よこづな)
相撲界の最高位です。引退するまで地位が保証されますが、不成績でも降格はない代わりに引退が求められるという厳しい立場です。月給300万円、運転手付きの車で国技館に乗り入れ可能です。横綱になるには、後述の大関の成績に加え、品格・力量ともに優れていることが審議委員会で認められる必要があります。
大関(おおぜき)
横綱に次ぐ地位で、かつての頂点です。安定して好成績を出している力士が到達できるポジションで、横綱昇進の足がかりにもなります。月給250万円で、ファーストクラス移動・複数の付け人など特別待遇を受けます。しかし、3場所連続で負け越すと関脇へ降格します。
関脇・小結(せきわけ・こむすび)
月給180万円の「三役」と呼ばれる幕内上位の重要ポジションで、上位力士との対戦が多く、実力の試金石となる階級です。
前頭(まえがしら)
幕内の中では最も多くの力士が在籍する階級で、実力もピンキリです。幕内の最下位クラスながら月給140万円で、横綱を破ると「金星」で報奨あります。
十両(じゅうりょう)
ここまでが「関取」で、給料(本俸)や待遇、個室などの特典がつくプロ力士扱いです。力士としての分岐点ともいえる大事な階級です。
幕下(まくした)以下
十両以下は「養成員」扱いで、給料はなく、雑用もこなす必要があります。ここから十両を目指して切磋琢磨している力士たちの姿が、相撲界の下支えとなっています。
番付(階級)はどうやって決まるの?
番付の決定は、6回の本場所ごとに更新されます。本場所の結果をもとに、日本相撲協会の「番付編成会議」で協議され、全力士の新たな番付が正式に決定されます。番付が決まるまでの流れは以下の通りです。
- 各力士の勝敗成績を集計
- 同じ階級の力士を比較し、成績に応じて昇降を判断
- 番付編成会議で案を検討
- 理事会で最終承認
- 大相撲本場所の約2週間前に番付表が発表される
つまり、「実力(成績)こそがすべて」の世界であり、派閥や人気はほとんど関係ありません。勝てば上がる、負ければ下がる。これが番付の基本です。
昇格の条件はある?
相撲の昇進・降格は基本的に成績によって決まり、8勝以上の勝ち越しで昇進の可能性が生まれます。そして、7勝以下の負け越しで降格の可能性が出てきますが、実際の番付変動は勝敗数だけでなく、他の力士との成績比較や現在の番付位置なども考慮されて決定されます。
幕内→三役
幕内力士が三役(小結・関脈)へ昇進するには、前頭上位で2桁勝利(10勝以上)を挙げることが目安となり、特に他の三役力士の成績次第で番付に空きがあれば昇進しやすくなります。
関脇→大関
関脇から大関へ昇進するには、三役で直近3場所の合計が33勝以上(例:11勝+11勝+11勝など)という安定した成績を収めることが条件であり、特に横綱や大関への勝利が含まれると評価がさらに高まります。
大関→横綱
大関から横綱へ昇進するには、2場所連続優勝または優勝と準優勝という成績に加え、「品格・力量ともに優れている」と横綱審議委員会に認められ、推薦を受けることが必要です。
まとめ
相撲の階級は、非常にシンプルながらも厳格な実力主義の世界です。昇格の条件は明確で、どの階級でも「勝ち続けること」が唯一の出世の道ですね。こうした明確な基準が、相撲という競技に「真剣勝負」の魅力を与え、長年にわたりファンを惹きつけ続けている理由のひとつです。これから相撲を観る方も、番付の仕組みや階級の違いを理解すると、もっと相撲が面白くなるはずです。応援する力士の昇進や降格にも一喜一憂しながら、日本の伝統文化を楽しんでみてください。